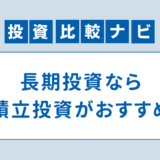NISAは個人の資産形成を考えた時に最初につかうべき制度です。NISAを利用するにはNISA口座が必要ですが、どの金融機関でNISA口座をつくるかで投資できる商品が変わったり、もらえるポイントに差がつくので、口座選びは重要です。
本記事ではNISAでおすすめの口座を徹底解説します。なお2024年からは新NISAが始まりますが、口座を選ぶ視点やおすすめの証券口座はこれまでと代わりません。初心者向けにどのような観点で口座を選ぶべきか解説します。結論は以下となります。(本記事にはPRを含みます)
| 1位 | 楽天証券 | 全体的にバランス良い。月10万円までポイント還元あり。楽天経済圏SPUもアップ。 |
| 2位 | SBI証券 | 楽天との2強。投信保有ポイントが貯まる。 |
| 3位 | auカブコム証券 | 提携銀行で優遇金利0.2% |
2024年からNISAの制度が変わる?
NISAは2024年度から制度の変更があります。今までは「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3つでしたが「一般NISA」「つみたてNISA」は新NISAの「成長投資枠」「つみたて背投資枠」に変更になります。(ジュニアNISAは廃止)
ただし変更といっても、基本的なコンセプト等は変わらず、投資できる金額や期間がアップされたので「拡充」という表現が正しいです。
なので、基本的には同じ制度なので、証券口座を選ぶ視点もこれまでと同様で変わりません。
証券口座の選び方
投資をするには証券口座が必要です。証券口座によって、投資できる商品や還元されるポイントにかなり幅があるので、NISAの証券口座選びはかなり重要になります。
取り扱い商品の多さ
のちほど詳しく説明しますが、NISAとは個人が長期的に資産形成をするために作られた商品でです。一般枠とつみたて枠がありますが、つみたて投資枠(現在のつみたてNISA)をメインと考えるべきです。
つみたて投資枠に投資できる商品は、金融庁で厳しい基準が設けられており、228本の商品です。220本のうち何商品を揃えているか、証券会社、銀行によって幅があり、ネット証券はおおむね200商品程度あり豊富ですが、メガバンクや地方銀行などはなかには対象商品を5程度しか揃えていない機関も多いです。
自分が投資したい商品が、その会社(証券会社や銀行)で取り扱いがないというのはもっとも避けるべきです。
メガバンクや地方銀行は、取り扱い商品が5~10本程度が大半であり、それに対しネット証券は150~200本程度の取り扱いがあります。必ずネット証券を選ぶべきです。
手数料はみるべき?
つみたて投資枠で投資できる商品は金融庁によって厳しい基準が定めらおり、販売手数料は0円、信託報酬は0.5%以下です。よって証券会社によって差はでてきません。
ポイント付与&優遇金利
NISAで意外と重要になってくるのが各社で行っているクレジットカード決済によるポイント還元です。つみたて投資枠の商品は、販売手数料が無料かつ信託報酬も低い商品ばかりなので、手数料であまり差がつきません。
その代わりポイントや銀行金利で差がつきます。クレジットカード決済すると、各社1%程度のポイント付与があります。また証券口座に各社グループの銀行を連結させると優遇金利をうけることができます。
| 楽天証券 | SBI証券 | マネックス証券 | auカブコム証券 | |
| 積立NISA対象商品 | 198本 | 205本 | 169本 | 193本 |
| 最低積立金額 | 100円~ | 100円~ | 100円~ | 100円~ |
| クレカポイント | クレカ0.5~1%
楽天キャッシュ0.5% 上限:月10万 |
クレカ0.5%~1.0%
上限:月5万 |
クレカ1.1%
上限5万 |
クレカ1%
上限5万 |
| 投信保有ポイント(オルカンの場合) | なし | 0.01% | 0.03% | 0.005% |
| 銀行優遇金利 | 年0.1%(300万まで
年0.04%(300万~ |
SBI新生銀行年0.1%
住信SBIネット銀行年0.01% |
なし | 0.2% |
| 使いやすさ | ◎ | ○ | △ | △ |
| 経済圏の強み | ○ | ○ | ☓ | △ |
| 特徴 |
無料でマネー本を読むことができる。 |
年100万円使えばクレジットカードゴールドの年会費が翌年から永年無料。 | 投資分析ツールが優秀。 |
NISAおすすめ口座3選
おすすめNO1 楽天証券
おすすめポイント
- 取り扱い商品が豊富
- クレカ還元1%の条件がない
- 銀行優遇金利が0.2%
| 取り扱い商品(つみたて投資枠) | 198本 |
|---|---|
| クレカポイント | クレカ0.5~1%
楽天キャッシュ0.5% 上限:月10万 |
| 投信保有ポイント | ほぼなし |
| 使いやすさ | ◎ |
おすすめ第1位は総合力で楽天証券です。本サイトでは第2位にSBI証券としているのですが、両者がNISA証券口座でダントツのトップ2であり、どちらのかの口座を選んでおけば間違いない状況です。
楽天証券の強みは、業界トップクラスの取り扱い商品数と、クレジットカードのポイント還元が上限で10万円(他の証券会社は上限が5万円)まで、できることです。
さらに初心者におすすめしたのは楽天証券のサイトの使いやすさです。楽天証券のサイトの使いやすさは有名で、間違いなく最も使いやすい証券口座です。
また楽天経済圏を利用している人にとって嬉しいのがSPUが0.5倍~1倍あがることです。楽天経済圏ユーザーは、楽天証券一択です。
さらに楽天証券を解説していると投資本を毎月無料で読むことができる破格のサービスがあるのですが、NISA口座を解説するとその上限の冊数があがります。投資本を1冊1500円とするとこれだけで少なくとも月5000円~1万円の価値があります。
おすすめNO2 SBI証券
おすすめポイント
- 取り扱い商品が豊富
- クレカポイント付与1%の条件が良い
- 投信保有ポイントあり
- SBI経済圏は勢いあり
| 取り扱い商品(つみたて投資枠) | 205本 |
|---|---|
| クレカポイント | クレカ0.5%~1.0%
上限:月5万 |
| 投信保有ポイント | 0.01%(オルカンの場合) |
| 使いやすさ | ○ |
おすすめ第2はSBI証券です。おすすめ第1位で紹介した楽天証券と双璧をなしており、どちらを選ぶかは重視するものによって変わります。
楽天証券と比較した際の最大の強みは、投信保有ポイントがつくことです。正確には楽天証券にも投信保有ポイントはあるのですが、SBI証券では、投信保有ポイントが毎月付きます。インデックスファンドの保有ポイントは0.01%など少額なのですが、運用残高が増えてくると、嬉しい金額になってきます。
またクレジットカードポイント付与の条件が、一般カードだと0.5%(年会費0円)、ゴールドカードだと1%(年会費1万円)なのですが、ゴールドカードの年会費が初年度に100万円のカード利用で永年無料になります。
楽天銀行でか、ゴールドカードの年会費はかかるので、初年度に100万円利用の条件はあるものの、達成できれば非常にメリットが大きいです。
おすすめNO3 auカブコム証券
おすすめポイント
- 取り扱い商品が豊富
- クレカ還元の上限が10万円
- サイトが使いやすい
- 楽天経済圏SPUがアップ
- 投資本を無料で読める
| 取り扱い商品(つみたて投資枠) | 193本 |
|---|---|
| クレカポイント | クレカ1%
上限5万 |
| 投信保有ポイント | 0.005% |
| 使いやすさ | △ |
おすすめ第3位は、auカブコム証券です。NISA口座の2強は、楽天証券とSBI証券と言われている現状ですが、auカブコム証券も悪くはありまえん。商品取り扱い数は、2社に引けをとりません。
そしてクレジットカード還元ポイントが1%なのですが、これは年会費無料の一般カードで適用されます。楽天証券や、SBI証券も、クレカポイントで1%が付与されますが、ゴールドカードでないと1%還元にはなりません。
またauカブコム証券のもう1つの強みが、連結銀行における優遇金利が0.2%になることです。通常のメガバンクに比べると100倍以上の金利であり、現状に日本で最も高い水準です。例えば、預金で1000万あれば、毎月2万円の利息がつくので非常に良いです。
これらのことを考えるとauカブコム証券は全く悪くない選択です。
最も選んではいけない銀行、証券会社は?
NISA口座で選ばない方がいいのは、リアル店舗をもつメガバンクや大手証券会社、地方銀行などです。NISA口座は絶対にネット証券で解説すべきです。
理由としては「取り扱い商品数」と「手数料」がネット証券の方が圧倒的に良いからです。
たとえばメガバンクだと、積立投資枠の商品が5~10本などとなっており、ネット証券の200本程度と雲泥の差です。また成長投資枠では、様々な商品が購入できますが、総じてメガバンクやネット証券の方が高いです。
これはメガバンクや大手証券会社は店舗費用や人件費がかかっているため、それが販売手数料に反映されているからです。一方でネット証券は無駄なコストがカットされているので、それが販売手数料に反映されています。
NISAとは?
税金非課税がメリット
NISAを日本語訳すると「少額投資非課税制度」となります。重要なキーワードは「非課税」でありこれは、投資で利益がでたり、配当金をえたりした時に、税金がかからないということです。
通常は投資の利益には約20%の税金がかかるので、非常にオトクな制度です。
つみたて投資枠と成長投資枠の違い
新NISAには2つの枠があり「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があります。この2つの枠は、同時につかってもいいですし、どちらか1つを使ってもいいです。以下に2つの枠の特徴を記載します。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
| 積立、分散に適した商品(金融庁が厳密に指定) | 株式、株式投資信託 | |
| 購入方法 | 積立て | スポット、積立 |
| 対象年齢 | 18歳以上 | |
| 非課税期間 | 無期限 | |
| 非課税投資枠 | 年間120万
(合計で360万) |
年間240万
(合計で360万) |
| 生涯投資枠 | 1800万(成長投資枠は1200万) | |
つみたて投資枠がメイン
金融庁は個人が長期的に資産形成するためにNISAという制度を発足させました。長期的に確実に資産を増やす投資といえば、インデックスファンドの積立て投資です。
つみたて投資枠では、初心者が失敗しないように金融庁で、投資できる商品を源泉しています。そして枠も、成長投資枠ではMAX1200万しか使うことができませんが、つみたて投資枠ではMAX1800万使うことができます。やはりつみたて投資枠がメインとなってきます。
つみたて投資枠は厳選された商品
つみたて投資枠で購入できる商品は金融庁で認定された商品のみで現在は228商品です。投資対象が幅広く分散せた投信が中心で、かつ購入手数料が無料で、信託報酬も低いものばかりです。厳選された商品ばかりでハズレがありません。金融庁の優良ファンドを選んで積立投資して欲しい狙いが伝わってきます。
商品は以下の3つに分類されます。
- 指定インデックスファンド192本
- 上記以外の投信28本
- ETF8本
注意点
NISAは税金がかからないので非常に有利な制度です。ただし税金がかかるのは、利益が出た時のみなので、利益がでなければNISAのメリットを享受することはできません。
逆に損がでている場合は、一般口座では使える損益通算が使うことができず、この点はNISAの唯一のデメリットです。
何に投資をすべきか?
NISA口座をつくったらどんな投資信託を選べた良いのでしょうか?万人にとって正解はありませんが、1つの考え方として、投資できる期間がどれだけあるかは重要です。
基本的な考え方としては、若い世代で投資する期間が十分にある場合は株式の比率を多くして、引退した世代は株式比率を小さくするという考えです。
株式は長期的にみればもっとも収益性の高いアセットですが、その分リスク(値動きの幅)が大きいです。投資期間が十分にながければそのリスクに耐えることができまるので株式比率を多くしても問題はありません。しかし投資期間が十分にとれなければ、リスクに耐えることができなくなります。